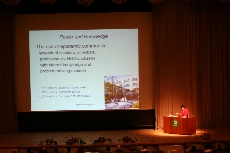第6回平和市長会議被爆60周年記念総会では、本年5月のNPT再検討会議で核兵器廃絶に向けた成果が得られなかったことを踏まえ、NPT再検討会議の結果を検証し、2010年までの「核兵器禁止条約の成立」及び2020年までの核兵器廃絶に向けた平和市長会議の取組について議論しました。
また、参加都市の市長が、①「核兵器廃絶が世界の大多数の市民の声であり、その声の代弁者である市長がそれを実現するために努力する」、②「各都市が自主的自立的な活動を始める」などと決意を新たにし、平和市長会議が新たな活動段階を迎えるに至った点で、意義ある画期的な会議となりました。
1 テーマ
- 核兵器廃絶に向けた都市の役割と取組み
-2020年の核兵器廃絶を目指して-
2 会期
- 2005年8月4日(木)~6日(土)
3 開催地
- 広島市
5 参加者数
-
- 20か国 92都市・4団体 205人
- (海外 19か国 54都市・4団体 144人)
- (国内 38都市 61人)
- 各国政府 14か国(欧州議会を含む) 18人
- NGO 7団体 20人
- 合計 243人 > リスト(Excel)
※海外の4団体は、全米市長会議、英国非核自治体協会、全イタリア市長会、ピースメッセンジャー都市国際協会である。
6 議決事項
7 報告
-
-
第6回平和市長会議被爆60周年記念総会報告書(議事録)
※これは会議当日の同時通訳の内容を加筆修正したものであり、実際の発言内容(英語、仏語)とは厳密に一致しない場合があります。 - - 議事資料(総会)
- - 議事資料(閉会式)
-
第6回平和市長会議被爆60周年記念総会報告書(議事録)
-
8月4日(木)
- 1 総会
- 役員の選任を行うとともに、今年の8月6日から来年の8月9日までを「継承と目覚め、決意の年」と位置づけ、国際気運をさらに高めるために様々な事業に取り組んでいくことを決議しました。
8月5日(金)
- 1 全体会議Ⅰ
- 対人地雷禁止条約の制定に携わったスーザン・ウォーカー氏の講演では、平和市長会議に対して、戦略的な行動計画の策定、政府、NGO、市民社会との連携、国際世論の喚起等の提言があり、明確なビジョンと決意を持って核兵器廃絶に取り組んでいくべきであるとの意見がありました。
- また、参加都市からは平和市長会議の取組みについて意見が出されました。主要意見は以下のとおり。
- ①2020ビジョン、核軍縮、核不拡散等平和市長会議の目標、大義を支持する。
- ②市長は市民に最も近い存在であり、平和のために中央政府とは違った対応をしていきたい。
- ③被爆者の活動に感謝し、被爆者のメッセージを伝えるとともに、被爆者と連携を図りたい。
- ④平和を推進していくうえで、将来を担う子供たちへの平和教育に力を入れていきたい。
- ⑤殺戮と暴力の代替として和解につながる「平和文化」を促進する必要がある。
- ⑥報復ではなく和解のために過去を記憶し、より良い未来を築いていきたい。
- 2 分科会Ⅰ
- 核兵器廃絶に向けた連携・推進方策について討議し、どの分野と協力していくかを戦略的に考えていく必要があるとの意見で一致しました。また、政府、NGOとの連携に加えて国連、自治体組織、議員等との協働が提案され、核軍縮議員ネットワークとの協力やEメールの活用等の具体的な事業内容や連携方法が提案されました。さらに、青少年を平和市長会議の活動へ参画させることの重要性も指摘されました。
- 3分科会Ⅱ
- 紛争を平和的に解決する方策について、被爆者が発してきた「和解」のメッセージをもとに議論しました。参加者からは、紛争の予防措置という背景において、現代の社会で持続的に発展させなければならない最も重要な方法は平和のための教育であるとの「教育の重要性」を訴える意見と、被爆者団体協議会に2005年ノーベル平和賞の受賞を求める取組みについて積極的な発言がありました。
- 2 被爆者の証言
- 被爆者であり、元平和記念資料館長の高橋昭博氏に被爆体験を語っていただきました。証言は絵と写真を用いて行われ、非常に臨場感あふれるもので、終了後、スタンディングオベーションが沸き起こりました。
- 3 全体会議Ⅱ
- 全体会議Ⅰ、分科会Ⅰ・Ⅱの概要が報告された後、全体チェアパーソンが、2020年の核兵器廃絶に向けて活発な討議を行うことができた点を評価しました。また3日間の議論は有益で示唆に富んでおり、その多様な意見を通じてそれぞれの参加者が新たな考えを学ぶことができたとの総評がなされました。
- 1 総会