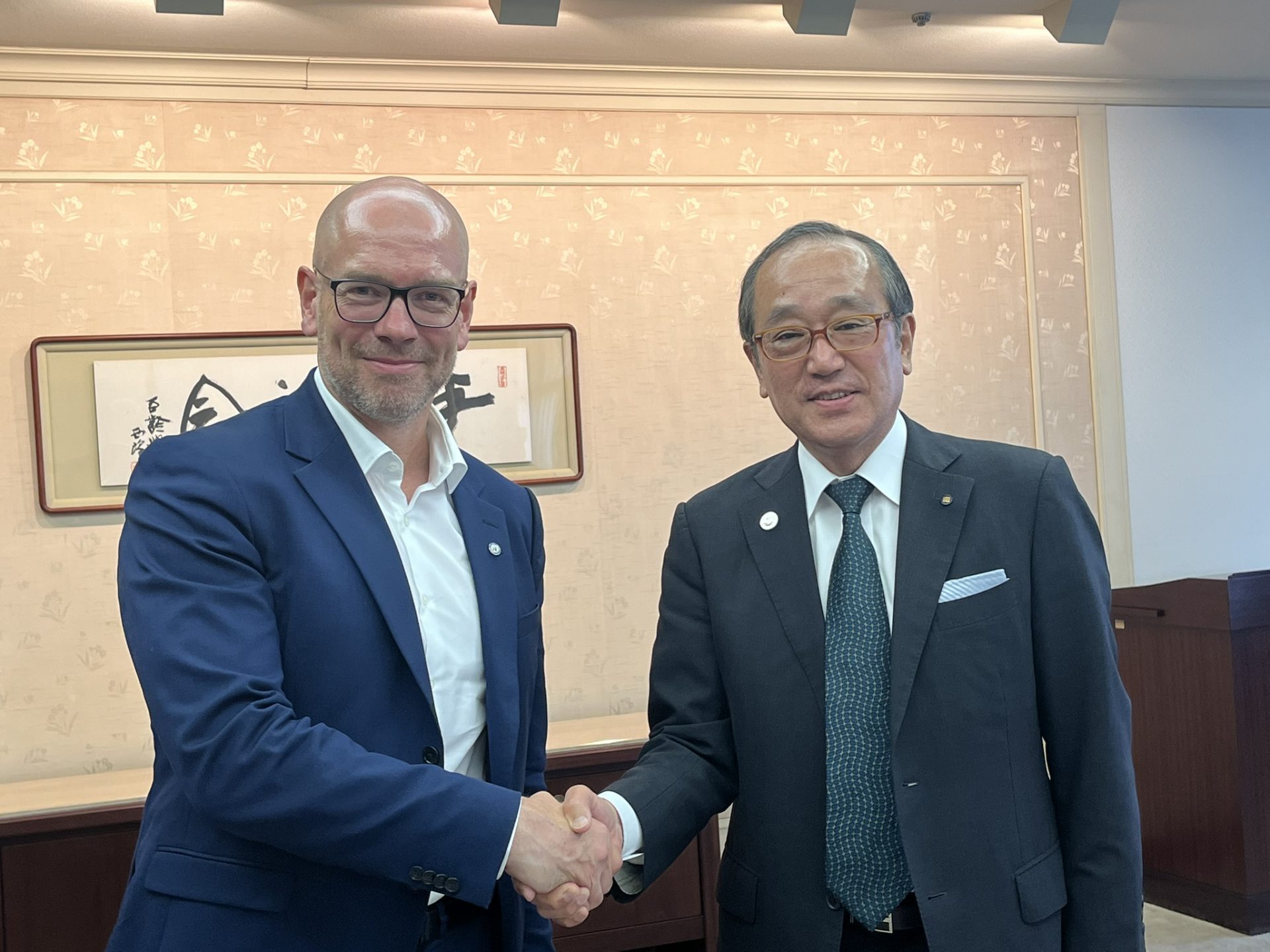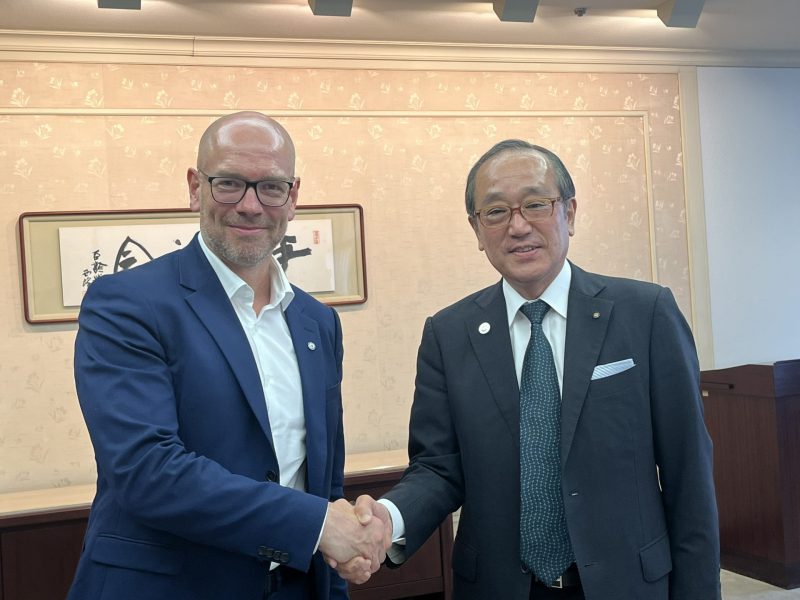今年5月18日から24日にかけて、国際連合軍縮研究所(略称UNIDIR)のロビン・ガイス所長が日本を訪れました。この研究所は第一回国連軍縮特別総会で設立されて以来、国連の唯一の軍縮研究機関として、45年にわたり、軍縮・安全保障の喫緊の課題について、独立した研究を行ってきました。私は長年、国連軍縮局で勤務していたこともあり、去年の4月から同研究所のフェローとして、その活動に従事しています。
今年は広島、長崎への原爆投下から80年という節目にあたり、この機会に日本を訪れるよう、私はガイス所長に強く薦め、今回の訪問に同行させていただきました。とりわけ、核戦争の影響を象徴する長崎、広島を訪れ、被爆の実相について理解を深めていただき、これらの悲劇の遺産が今日の軍縮努力に反映されることが、今回の訪日の重要な目的でした。
まず、ガイス所長は東京で英利アルフィヤ外務大臣政務官を表敬訪問し、中村仁威軍縮不拡散・科学部長など外務省幹部と懇談し、UNIDIRと日本政府との連携について話し合いました。また、軍縮議員連盟会長の猪口邦子参議院議員、公明党の平木大作参議院議員と意見交換をしたほか、国連大学において新興技術と宇宙に関する安全保障に関するシンポジウムに参加し、日本国際問題研究所主催のラウンド・テーブルで、AIなど新興技術の軍縮・安全保障問題への影響について専門家と議論しました。
その後、ガイス所長は長崎を訪れ、5月22日に長崎市役所で鈴木史朗長崎市長を表敬訪問し、UNIDIRと長崎市のパードナーシップの強化や、核兵器の廃絶に向けた共同研究の推進について意見交換を行い、平和で核兵器のない世界への共通のコミットメントを確認しました。
また、ガイス所長は長崎大学を訪問し、永安武学長や核兵器廃絶研究センター(RECNA)の吉田文彦所長と会談し、同大学の平和教育や共同研究の実績の説明を受けるとともに、長崎大学との今後の連携強化ついて話し合いました。UNIDIRは、昨年RECNAと提携関係を締結しましたが、ガイス所長は同センターの研究者や学生と懇談したほか、RECNA主催の公開講演会で、平和と軍縮における対話の重要性について講演しました。UNIDIRは有意義な対話の促進に注力しており、それはガイス所長の長崎訪問の核心でした。同所長は、核兵器国間での地政学的緊張が高まり、外交上のコミュニケーションが希薄になる中、対話は不可欠であり、世代、文化、イデオロギーを超えた声が真に届くような対話を促進する必要性を強調しました。
ガイス所長は、訪日の最後の数日間、広島を訪れ、5月23日に広島市役所で松井一實市長と面談し、広島とUNIDIRの協力の機会を模索しました。松井市長は、平和と軍縮の分野における共同研究と教育の実施・促進のため、UNIDIRの活動拠点として広島を活用することを提案しました。この会談に同席して、戦争の記憶を未来世代のための平和の礎にしたいという共通の使命を感じました。
また、ガイス所長は日米共同の研究機関であるである放射線影響研究所を訪問し、同研究所が戦後一貫して行ってきた原爆の被災者への影響についての研究成果の説明を受け、今後の同研究所との協力の可能性を模索しました。また、ガイス所長は国連訓練調査研究所(UNITAR)広島事務所を訪れ、三上知佐所長をはじめ UNITARのスタッフと面談し、同事務所の活動とUNIDIRとの協力について話し合いました。
その後、ガイス所長はヒロシマ平和研究教育機構主催の学生向けの公開イベントで、将来を見据えた平和と安全保障について講演をし、国連軍縮研究所の視点から、世界における核軍縮の現状を解説、最初の被爆地である広島が被爆の実相を伝える意義を強調しました。また広島市立大学の広島平和研究所の大芝亮所長をはじめ、地元の大学の教授陣や研究者と懇談し、平和と軍縮分野における研究・教育における協力について、幅広く意見交換を行いました。
なお、ガイス所長は、長崎と広島において被爆の実相の理解に熱意を示し、長崎原爆資料館と広島平和記念資料館で、数多くの展示物、写真、模型を通して、長崎、広島への原爆投下とその影響について詳細に学ばれました。また、長崎では三瀬誠一朗氏の被爆の経験談を聴かれ、広島では森重昭氏と佳代子夫人とお会いになり、ガイス所長は被爆者の証言に深く心を打たれていました。特に森夫妻との面談は、昨年7月にジュネーブで開かれた第11回NPT再検討会議第2回準備委員会のサイド・イベントで、森氏が数十年の歳月を費やして、広島で被爆して亡くなった12人のアメリカ人捕虜の身元確認をした活動を記録したドキュメンタリー映画『Paper Lanterns(紙灯籠)』の上映会をUNIDIRが開催しため、ガイス所長にとっては特別な意味を持つものでした。
たった1週間の滞在でしたが、ガイス所長にとっては初めての訪日であり、被爆地を訪れ、被爆者と直接話をされ、被爆の実相の理解を深められました。この訪問は、広島と長崎の悲惨な経験が今もなお、核軍縮の世界的な取り組みの原動力となっていることを認識する機会になったようです。これにより、ガイス所長は、国連軍縮研究所が軍縮や安全保障の分野の研究を通じて、国際平和に貢献するという使命を強く感じられたと思います。
[写真提供:相川専門委員]